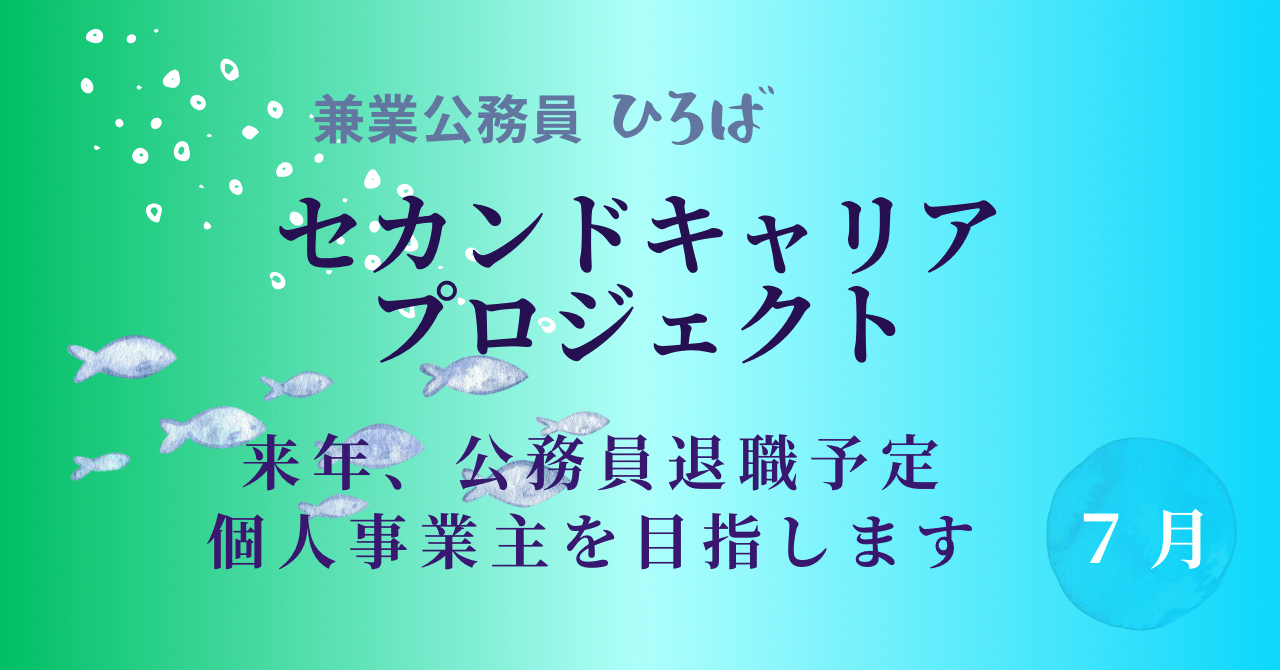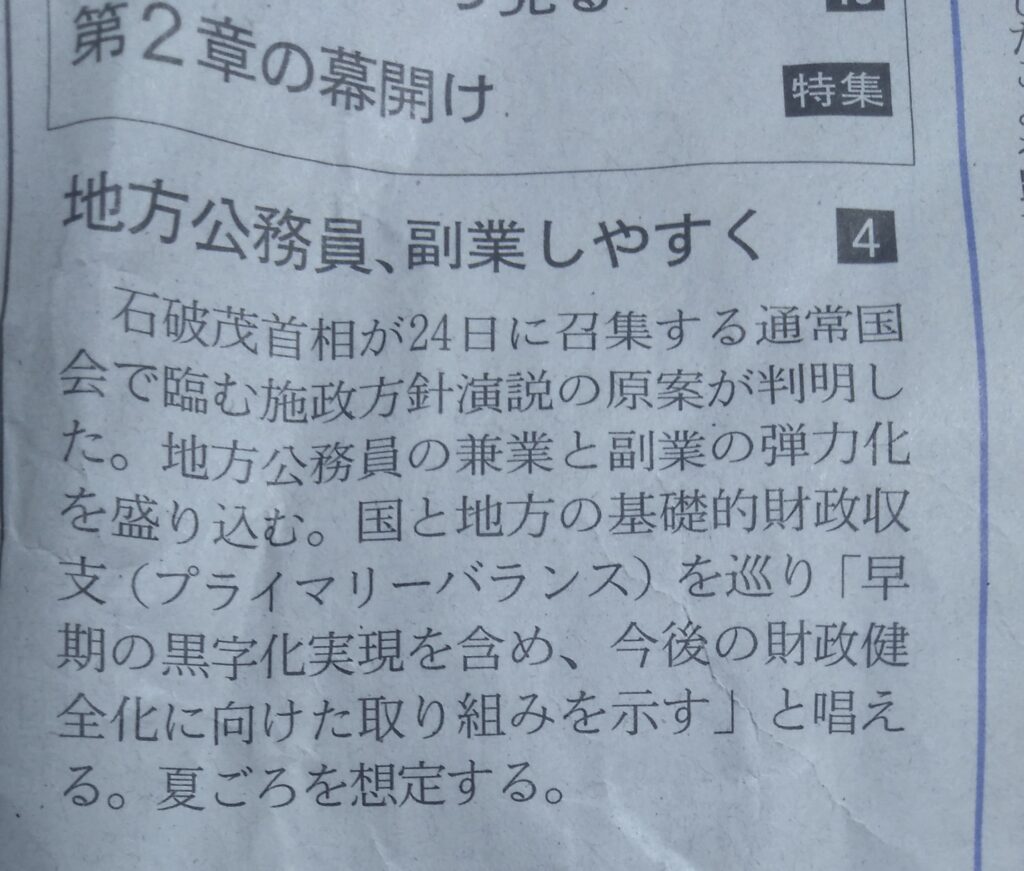国が、地方公務員の兼業規制を緩めて、人材や能力を世間で活用してもらおうという流れができてきているという話は、ニュースにもなっているし、このサイトでも過去に取り上げた通りです。
ネット記事だと、昨日の夕方ごろに報じられた話題。私は自宅で日経を紙で取っているので、今日の朝刊1面にデカデカと出たほうで全文を確認した。記事要旨総務省は地方公務員の兼業や副業を促す。地方自治体向けの許可基準を示し、営利企業から報酬を得て働くことができると明確にする。現状の原則禁止から緩和し、地域に貢献し課題解決につながる活動を幅広く認める。地方公務員の働き方の自由度を高めて人材確保も目指す。という文章から始まる記事で、総務省の分科会が基準
ところが、逆のケースもあるみたいなんですね。
公務員の兼業規制のハードルを、「水位」に例えたとして。ある池(自治体)の水位が、現にかなり低かった(兼業規制が緩かった)とします。そこへ、国が示した地方公務員の兼業規制緩和によって、国の指針では、かなり高い水位から中くらいの水位への変化が起きたとします。
そうなったとき、中くらいの水位より低かった、その池(自治体)の水位はどうなるのでしょうか。変わらないのか、それとも中くらいに上がってしまうのか。
おはようございます。 兼業公務員ひろばです。 私が勤務する市役所は、正職員約2,400人、会計年度任用職員約1,600人、合計約4,000人の職員数です。 営利企業従事許可について パートタイムの会計年度任用職員は、副業禁止の対象ではありません。営利企業従事許可を得る必要はなく、届け出をするだけで副業ができます。 正職員は、営利企業の役員等になること、自ら営利企業を営むこと、報酬を得て他の事務事業に従事することが制限されており、各任命権者の許可を受けた場合に限り従事することができることとなっています。 私の市で令和5年度の営利企業従事許可がされた件数は、120件です。 その
こちらのお方。西日本の某県庁所在市役所の職員。noteでは実名を出していないようなので、Nさんとしておきますが(ジチタイワークスとかみるとライフワークの方で肩書付きで登場されてるので別に隠すこともないかと思いますが)、この方の勤務先はもともと兼業規制が緩くて、結構バリバリ余技で活躍されてたようです。
上記noteから引用します。
私の市で令和5年度の営利企業従事許可がされた件数は、120件です。そのうち3件は私です。多くは不動産(アパートの家賃収入等)だと思われます。
(中略)
昨年度から、これまで許可していたものを見直し、国家公務員を参考に、許可基準を厳しくしようとする動きが人事課内部で出ていました。
明らかに時代に逆行している!人材が逃げていくよ!と私は強く訴えました。これは、市としての組織の見解か?(そんなことは絶対に無いはず!)
担当レベルの考え方ではないか?(そうに決まっている!)きっと、市全体の考え方ではなく、今の人事課だけの狭い考え方だと思いましたがパラレルキャリアのどちらかを選ぶことを、事実上、迫られる状況でした。
人事課は何を考えたんでしょうね。邪推すると、ウチの役所は規制が緩すぎた。文句言われるの嫌だから総務省通知レベルに合わせとこう、てなところじゃないでしょうか。
総務省の示した基準って、結局は地方が人手不足だから、公務員も余った時間に体を使って地域貢献する副業はOK、ということなんですね(実際にはそれは最狭義の解釈だと思われ、もう少し広げても大丈夫だと思うが、これを守っていれば文句は言われない)。
で、この方の勤務先の担当者はそれに合わせようとしてしまった。
残念なことですね。Nさんは、ライフワーク無き人生はあり得ないと、退職を決断し、R7年度末退職みたいです。それを5月に言わないといけない職場。なかなかですねえ。
結局、公務員の兼業規制って、安定してるくせに副業までするなんてズルいとか、民間と癒着が生じるのではないかとか、役所の外から文句を言われないように規制があるんだ、的な話がよく出るんですけど、私は違うと思っています。
本当の敵は中にいて、「余技無き平凡な職員たちからの嫉妬(反乱?)」を恐れて、相続不動産経営とか、やむを得ない程度までしか副業解禁できないんじゃないかと思ってます。
地元の人手不足に対応することも、やむを得ないと理解を得られるが、自己実現のための副業はダメ、という。
何とも人権侵害職場だよ!そんな職場で市民の安全や快適な生活を守っていけるのか、と一喝してやりたいですね。