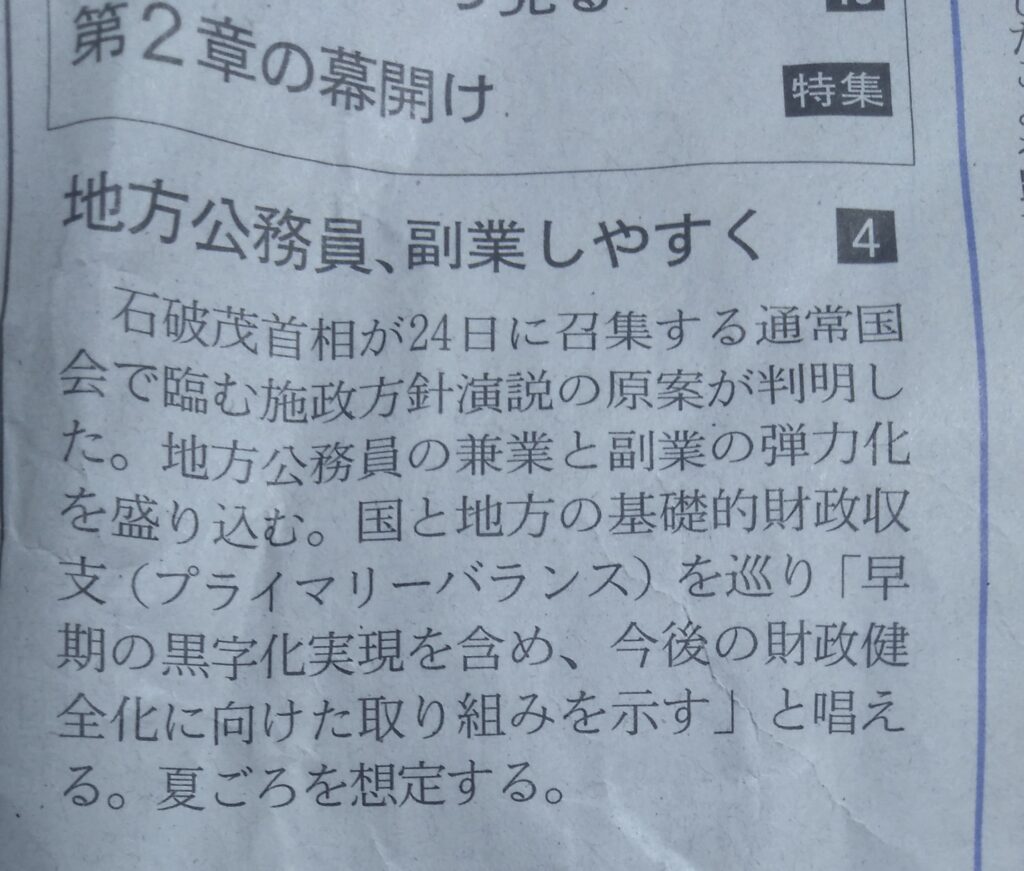ネット記事だと、昨日の夕方ごろに報じられた話題。私は自宅で日経を紙で取っているので、今日の朝刊1面にデカデカと出たほうで全文を確認した。
総務省は地方公務員の兼業や副業を促す。地方自治体向けの許可基準を示し、営利企業から報酬を得て働くことができると明確にする。現状の原則禁止から緩和し、地域に貢献し課題解決につながる活動を幅広く認める。地方公務員の働き方の自由度を高めて人材確保も目指す。【関連記事】総務省の分科会が新基準を検討し、自治体に提示する。町おこしや移住者支援などのほか、地域住民の生活維持に欠かせない仕事も認める。例えば過
記事要旨
総務省は地方公務員の兼業や副業を促す。地方自治体向けの許可基準を示し、営利企業から報酬を得て働くことができると明確にする。現状の原則禁止から緩和し、地域に貢献し課題解決につながる活動を幅広く認める。地方公務員の働き方の自由度を高めて人材確保も目指す。
という文章から始まる記事で、総務省の分科会が基準を検討するという。具体例としては
町おこしや移住者支援などのほか、地域住民の生活維持に欠かせない仕事も認める。例えば過疎地のコンビニでの労働や新聞配達といったケースを想定する。
とのこと。広義のエッセンシャルワークといったところだろうか。
解禁されるのはエッセンシャルワークだけで、自己実現につながる仕事は解禁されない
以前からこのサイトでも、この、地方公務員の副業拡大路線については、次のとおり何度も言及しているが、このサイトの目的(公務員の自由な副業の実現)との関係で言えば、一番肝心な部分、すなわち自分がやりたい(=自己実現につながる)仕事には解禁が拡大されないと思われる。
今日の日経新聞1面に、「地方公務員、副業しやすく」という見出し(中の面の記事のヘッドライン)が載っていた。石破内閣の通常国会での施政方針演説に、地方公務員の兼業と副業の弾力化を盛り込む方針であることが判明したという記事。施政方針演説案って厳秘じゃないのか?誰がリークしたんだよ、って思わなくもないが、それはさておき、日経の記事にある、施政方針演説案の骨子だか何かを引用したと思われる部分、兼業しやすくなるよう制度を改め「地域の中の方々が力を発揮できる環境を整備
前回の投稿で、石破総理の施政方針演説の中で公務員の副業規制の緩和が盛り込まれるというニュースが速報された件。実際にはどうなったのかというと、こんな感じ。(若者や女性にも選ばれる地方) 第1の柱は、「若者や女性にも選ばれる地方」であります。若者や女性が「楽しい」と思えるような新しい出会いや気づき、そこから生まれる夢や可能性が重要です。 新たな人の流れを太くするため、いわゆる関係人口に着目し、都市と地方といった二地域を拠点とする活動を支援します
前回、国家公務員の兼業規制の緩和(正確に言えば、必ずしも広がっているとは言い難いので、明確化というべきかも)について紹介しましたが、地方公務員についても兼業禁止規制が緩みつつあると言われることがあります。今回の記事では、国の通知に先んじて副業緩和の先陣を切ったとされる神戸市と生駒市の制度を紹介します。神戸市 地域貢献応援制度(内閣省資料に基づく抜粋)2017年4月~生駒市「地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事制限の運用について」2017年8月~【対象職員】●一
だって、本件は結局のところ、人手不足が続く地方において、公務員を民間企業、地域の商店や農林水産業の労働力として活用しようという目論見で副業を解禁しようとしている話だからだ(上記の当サイト記事「…解禁されつつあるという傾向は本物か②」を見てほしい)。
今回の日経記事には、「公務員の働き方の自由度を高めて人材確保を目指す」とあり、今回の兼業範囲拡大の動きの「背景に公務員のなり手不足がある」とも指摘している。
確かに、副業が強く規制されていて働き方の自由度が低く、それゆえに公務員人気が落ちているというのは、一面の真実だと思う。ただ、今回の対応は、ちょっとズレているような気がしなくもない。なぜなら、
家業があり、その手伝いが必要だから、地元の若者が、家業との兼業が難しい地元の公務員になろうとしない⇒だから地方自治体が人材難
というロジックだけで、公務員の魅力低下を説明しきれるかが疑問だからだ。
私が思うに、自己実現につながるような副業(クリエイティブ関係など、自分のスキルを活かしたビジネス…要するに何らかの小遣い稼ぎ)が現に厳しく規制され、たとえ今後解禁されても、副業したら職場で後ろ指を差されるような雰囲気の役所勤めが息苦しいから、公務員のなり手が減っているのではないのか。
少子化対策と同じで、ズレてる取組
少子化対策と称して、国も地方自治体が(すでに子どもを設けている)子育て世帯向けの対策ばかりしているという取組のズレがあることは有名だが(一番必要なのは、出産適齢世代の非婚化・少婚化対策だろう)、上記のような公務員の人材対策にも同じズレを感じざるを得ない。
地域貢献のエッセンシャルワークへの副業解禁も確かに必要だろう。しかしそれだけでは不十分だ。
多少年収が下がってもいいから、雇用の安定を維持しつつ、労働時間も抑えた上で、地域貢献などと世間に説明しやすいタガをはめずに、信用失墜に当たるような風営法業種や守秘義務違反となる業務でない限り副業を認める、くらいでないと、公務員の魅力は向上しない。